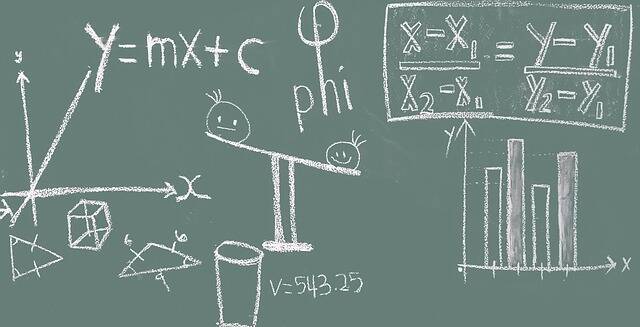続き物っぽいやつ。以下過去記事。今回は結果が良くなかった時期にスポットを当てて考察します。
前回のあらすじ
- 総資産1.6億円になったらリタイアしたいよ
- 株式と債券(日本ではない)でポートフォリオを組むと円高になった時怖すぎるよ
- じゃあ円高対策/大暴落対策用で生活費の14年分を日本円にして残り全部株式(日本を除く)でええやん!!!
- 起点日から30年間の最終結果を1日ずつずらして調査してチャートにしたら生活費13,14年を日本円にすると世界恐慌を除いて、ベトナム戦争時期やらITバブル崩壊+リーマンショックの2大暴落も1.6億円あればなんとか耐えられそうだよ
※但しITバブル崩壊+リーマンショックは30年のチェックではなく23年しか計測できない点がちょっと残念。2000年~2030年になっちゃうので。
と言う感じでした。で、改めて以下がその図です。私の私による私のためのチャートです。他の人が見ても意味ないですが、参考になったりならなかったりするかもしれない。生活費と総資産と手元の現金の比率を合わせればこうなるので。

現金7年分の確保だと株式投資の額がガンガン減って、復活時期に間に合わなくなってマイナスになってますが、14年の現金を持てば、1960年代も生き延びることができていることが分かりました。ITバブル崩壊+リーマンショックもかなり余裕がありそうです。
ただ、やはりベトナム戦争時期の詳細はちょっと知りたいなって思ったので、その日付だけピックアップします。
ベトナム戦争周辺チャート確認
1955-09-19から30年間だけピックアップしてチャートにします。この時期が特に成績が悪かったので。条件はこちら
今回のシミュレーション値
- 将来円高により株資産は75%減額されていることにします
- 総資産:1.6億円
- 現金:生活費14年分と7年分の二つなんとなく見る
- 株 :残りの現金全て * 0.75倍 (今よりだいぶ円高になったことを想定)
- 生活費:5,448,000円 ( 約545万円 / 年 )
- 生活費14年分は十分安全な期間設けているので現金補充はしないよ
- 生活費7年側は株式が前回生活費を確保した時点の株価が現在の株価以下になったら株式を売却して生活費および現金プールに補充します。(※ITバブル崩壊+リーマンショック対策)
- 配当金は考慮無しなので、少し厳しめに採点してる形になります(※逆に言えばこれで耐えられれば余裕でリタイア可能っぽそう)
こんな感じで行きます。14年分側の現金補充については年金をもらえる時期とかその時の体調とか次第で株式を売却してある程度現金にする可能性もありますが、一旦こんな形で。
生活費7年の場合

1979年後半に株式が復活しつつあったのでそこで株式を売って現金を補充しています。
が、株式の運用益がその後に無くなったので、資産は目減りする一方です。一応、ITバブル崩壊+リーマンショックという2回の暴落に耐えられる形にしておかないとアーリーリタイア(セミリタイアではない)はちょっと苦しいし、いつもそれ考えて生活するのは嫌だなって思ってます。
生活費14年の場合

最終的に生活費14年を持っていた方が安定しました。これは最初から14年用意していたことで、都度の補充が不要になったことからです。補充するタイミングは前回補充したタイミングより株価が上になったタイミング。そうすると、結局株式の運用益が少なくなるため、結果的にパフォーマンスが悪化したと考えられます。
そこでふと思いました。
株式投資というものは、1秒でも早く投資して、できるだけ長く投資した方が圧倒的にパフォーマンスが良いということ。
であれば、30年間の最初の14年間は、無条件で現金から生活費に割り当てて、最後の16年は株式で生活費を賄う、というのはどうでしょうか。
「最後の7~15年目で暴落が来たらどうするんだ!」
という声が聞こえてきますが、それってつまり、そこに至るまではバブルが発生していて運用益は潤沢にあるってことですよね。最後までの運用益が乗ってれば最後の暴落なんて些細なものですし、5年目ぐらいに大暴落が来ても普通に9年の生活費あるから大丈夫じゃね?っていう妄想。
ということで、妄想はおしまい。とりあえず、この最悪時期である「ベトナム戦争」付近でチェックしてみましょうか。
ベトナム戦争_最初の生活費14年を使い切るパターン
先ほどと同じ条件、同じ日からスタート。違いは現金を14年いきなり消費でいきます。

いきなり結果を出してくれた。好き。
比較すると、
- 7年生活費:4000万円フィニッシュ
- 14年生活費:6000万円フィニッシュ
- 14年速攻使い切り補充無し:9000万円フィニッシュ
とはいえ、たった1箇所で、単に運が良かっただけの可能性大です。ただ、可能性はでた気がするので、まーた1927年12月から2003年ぐらいまでを1日ずつずらして検証してみました!
最初の生活費14年を使い切る全パターン30年分
ということで、生活費14年の中で、
「前回売ったタイミング以上の終値なら株を売却して生活費へ(青線)」
VS
「最初から14年現金売って生活費にして無くなったら株を売っていく(赤線)」
で毎日バトル開始です。

圧倒的に「最初から14年現金を速攻使ってから株を売っていく」というスタイルが強いことが分かりました。状況は関係ありません。14年間、ひたすらプールしてある現金で生活して、株投資側の資産を減らさないように努めればいいだけです。
ただ、1930年前後のほんの一瞬だけ、都度株式売却の方が強い時期が本当にちょっとあったかな?っていうぐらい。ただ、超絶誤差でちょっと負けるぐらいの結果なので、全く気にする必要はないでしょう。というか世界恐慌なので皆氏ぬ。
・・・なるほどね。これが「真実」ってことね。
「投資は1秒でも早く、1秒でも長く市場にいた方がいい」
の真実。
今回の条件は最初から14年連続で現金を生活費にすることで「1秒でも長く市場にいた方が良い」を実践した結果です。なるほどねぇ・・・正直予期せぬ結果で驚いています。真理に到達しました。ありがとうございます。
つまるところ、過去100年に置いて、「14年あれば株価は右肩上がりする」が世界恐慌の最初だけを除いて100%達成できているということです。リタイアした直後に大暴落しようが、暴騰しようが何も起こらなかろうが、とにかく14年待ってればいいと。
とはいえ生活費14年分使った後は株式に完全にゆだねることになるので、ちょっと怖いのも事実。65歳になって目標達成額に来たら株を売れば良いと思いますが。
ということで、生活費13~16年を最初から保持しておいて、初手現金を売っていくチャートを並べてみたいと思います。怖いので15年、16年持ちたくなるのが人情というものです。13年は気まぐれでやってみました。
以下為替リスクアリです。株式側は75%減状態でスタートしてるので、16年分の現金を持った方が開始地点では有利です。
最初の生活費13~16年を使い切る全パターン30年分(為替リスクあり)

なんと大体の期間、生活費13年が勝ちました。
この結果は面白くて、株式は円高により株式の価値を75%にしている状態で現金を持てば持つほどお得になるのですが、総合的には13年程度の日本円をもって最初の13年間で使い切るのが一番いい結果になったということです。
逆に16年は持ちすぎで、運用益が13年と比べて3年分低いことから単純に結果が悪いです。ITバブル崩壊+リーマンショックからの22年後の世界でさえ、16年の方が成績が悪いのです。
が、世界恐慌やバブル崩壊直後部分の底値付近だけ、13年がビリです。
まぁ、世界恐慌を見たらリタイアできないので・・・
正直現金をを増やしすぎたり減らし過ぎたりすると、今度は「円高・円安問題」が浮き彫りになってくるのと、「大暴落2回分に耐えられない」とかのリスクも生じるため、アーリーリタイア時の日本円保有率は生活費13~14年で良さそうです。
じゃあ、
「最初に円を売ってる時が円安で、売り終わったら円高になったらどうするんだ!」
って意見が聞こえてきましたが、上記の結果通り、そもそも最初から株式は75%減スタートであらかじめ対応してますし、円安時代が来たとしても、最初の14年のうちにその円安の現金で生活費で使ってしまうので生活費に影響が出るころにはポートフォリオ的には影響を受けない・・・ことになってたら嬉しいなぁでいきます(※適当)
で、株式が最後はすこぶる快調になるのは分かっているので、円高になっても為替分のダメージも十分ペイできることが期待できます。というか初手から株式資産は75%オフでシミュレーションした結果なんだからこれ以上求めるな!!!
もしリアルでやるなら、13年を現金を確保して、残り1年は自由投資枠とか、TLTの長期債で為替ヘッジ無しで挑むか、RPARのようなポートフォリオを組んでも面白いかもしれません。その辺は匙加減。円安円高読める人はその辺上手く考えてください。私は良く分からないので14年分の日本円、もしくは少なくとも10年分の日本円、4年は疑似RPARとかTLTとか持つかもしれない。
まとめ
- 大暴落2回分を想定して14年日本円持つと良さそうだよ。ドルと日本円の比率を50:50~60:40ぐらいをもってからリタイアした方が良さそうな気がするよ
- まさかの14年連続現金から生活費を消費して、その後ノーブレーキで株式100%運用した方が結果的に生きていられるよ。氏ねば助かるのに。
ということで、今回はここまで。次回は、さすがにノーブレーキでブイブイ言わせるのは怖いので、株価が前回よりxx倍高くなったらその年は売却して生活費にする、というのをシミュレーションしたいと思います。
※以下続きです。